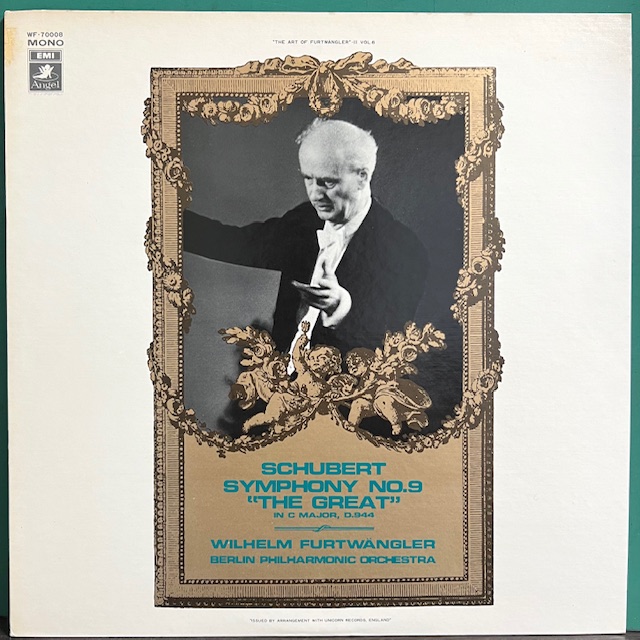熱い夏の日、涼を求めて家を脱出しましたー。
旅を終えまた旅に出る。
「人生は旅の途中、そうだ、奈良に行こう。」
寒い日も嵐の日も酷暑の日においても、歩みを止めてはならないーそう思い…そこから日本が始まったという古の奈良の社寺を巡る旅に出かけました。
ボクが初めてこの地を訪れたのは60年ほど前になります。猿沢の池から見た興福寺の五重塔を背景に写した修学旅行の集合写真、パッと目の前に現れた「夢殿」、広大な平城京跡、そこで友と戯れた中学生の頃が、今でもモノクロ写真のように蘇ります。
その後、日本の歴史に興味を持ち、古人に想いを馳せ、巨大な木像に圧倒され、季節の移り変わりとその美しさを愛で、ちっぽけな自分が年齢を重ねるたびに何度か訪れた奈良です。
今回訪れたのは「室生寺」から〜です。
「我が身をば 高野の山に とどむとも 心は室生に 有明の月」
ー伝 空海ー
室生寺は奈良時代の白鳳9年(680)に天武天皇の勅命により建てられたと伝わり、国宝の釈迦如来立像は平安時代初期を代表する榧(かや)の一木造りで、2.3メートルを超える堂々とした姿に圧倒されます。時代は下り〜一千年を超え、桓武天皇、空海から桂昌院の名も。
また、室生寺は女人禁制の高野山に対抗して「女人高野」とも称され、室生山での修行や真言宗の重要な道場として厚い信仰を集めています。
なんといっても驚きは、宇陀市室生の険しい山と河川に囲まれた傾斜地に五つもの国宝、重要文化財を持ち、千年以上も信仰、巡礼の聖地としてここに今もなお佇んでいる事であります。
猛暑とはいえ、心身の底から涼を感じた古寺巡礼の始まりでした。